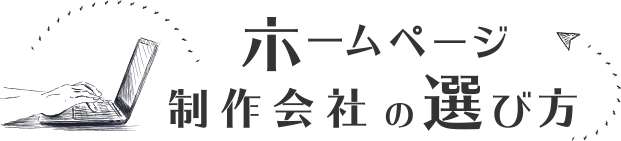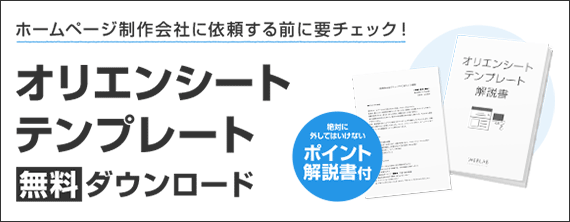制作のポイント5:作ってからがスタート
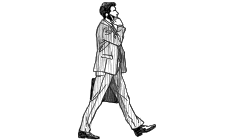
Webサイトは作って終わりではなく、作ってからがスタートです。
私たちウェブラボでは、定期的に数字を計測してホームページの様子を見ています。
ちなみに定期観測している数字にはどんなものがあるのか紹介しますと
◆毎日計測
▼広告(SEM)
-
リスティング広告の数値
→インプレッション数
→クリック数
→コンバージョン数
→広告費
▼SEO
- 主要キーワードの検索順位
▼反響
- メールでの反響数
- 電話での反響数
これらを毎日計測し、ホームページの反響や効果を測るためのベースとなる数字を積み上げていきます。
◆毎月集計
毎月集計する数値は、毎日計測していた数字の一か月分のほか、以下の数字を取ってきます。
▼反響
- 媒体ごとの資料請求数や問い合わせ件数
- 商談に至った件数
- プラン別の成約数や商品別の成果数
▼アクセス解析
Webサイトのアクセス解析
→セッション数
→流入シャネル
→参照元サイト
→検索クエリ
→直帰率の高いページ
→離脱数の多いページ
1か月でどれくらいの売り上げがあったのかという目的達成度合い、そしてそれに付随してくる数字の良しあし、それぞれの状況を把握します。
その後、チームごとの売り上げと問い合わせ件数、商談に至った件数などを社員全員に対してシェアしています。
期待した効果が出ているかモニタリングしよう
なぜこのようなことをするのかというと、
- 数字の異変に気付くため
- そのサイトが上昇トレンドにあるのか、その逆かを見極めるため
- 社員が数字に対して敏感になってくれるから
という3つの利点があるからです。
これを何年も続けていれば、だいたいの数字がわかってくるようになり、そのWebサイトが出せるパフォーマンスのレンジがなんとなく見えてきます。
そういう状態まで行けば、予想の範囲はある程度のブレが出てくるものの、何が問題でブレているのか、そのブレは改善の余地があるものなのか、明白になってくるのです。
予想のブレには季節要因や商機、その他外部状況などが原因であれば、問題はありません。
当社はホームページの制作請負を主要なビジネスとしているため、営業日が少ない月、特に2月や5月、休暇や有給取得の多くなる8月、1月なども数字の低下が出やすくなります。そうした下げは無視しても構わないと考えています。
問題はそうした要因がないにもかかわらず、顕著な落ち込みが見られる場合です。
あるケースでは、資料請求から商談に至る件数が昨年同月比と比較して、顕著に悪くなり、それが翌月も続いたことがありました。
こういったケースは、何らかの原因がある可能性が高いため、早急に手を打つ必要があります。トークスクリプトが徹底されていないなど、自分たちに問題があることもあるので、改善の手はずを整えていきます。
こうした数字の落ち込みは、定点観測していなければ気づけません。
Google Analyticsで何を見ればいいの?
そのために、もっとも手っ取り早くかつ正確に数字を把握できるのが、Google Analyticsです。いろいろな解析ツールがありますが、Google Analyticsではできないことがどうしても出てきたときに、ほかのツールを使いましょう。それまではGoogle Analyticsで十分です。
Google Analyticsで何を見るかというと先ほども上げていたこれらの数字です。
- セッション数
- 流入チャネル
- 参照元サイト
- 検索クエリ
- 直帰率の高いページ
- 離脱数の多いページ
どのくらいの数のセッション数があるのかをまず把握して、全体の増減を見ていきます。
極端に減っているならば、流入チャネルや参照元などをチェックして原因を調査します。
また検索クエリの状況は定期的に追いつつ、SEOの状態と絡めて分析を行います。また、アクセス数が多いにも関わらず、ページの直帰率が高い、あるいは離脱数が極端に多い場合は、原因について仮説をたてて改善していきます。
わずかこれだけの数値を見るだけでも、いろいろな状況を把握するため手がかりになります。ぜひ定期的に追ってみて下さい。
リニューアル後に反響減…その時まず何を確認すべき?
ホームページのリニューアル後に反響が落ちることもまれにあります。期待した効果を得られないどころか、いままで出ていた成果もなくしてしまうのですから、管理者側のショックも大きいでしょう。
もしもリニューアル後に反響が落ちてしまったら、まずは事前に仮説を立てましょう。
リニューアルを境にして反響が落ちるのは市場の変化がもたらしたものではない点=リニューアルに何らかの原因がある=です。
リニューアルが原因で反響が落ちる理由は2つしかありません。
- 反響率の低下
- アクセス数の減少
どちらが原因なのか、リニューアルの前後で、アクセス解析の結果を比較すれば、おのずと答えは導き出されます。
もし反響率が低下(アクセス数は下がっていないが反響は減っている)したのが原因であれば、ニューアル前後で、直帰率や離脱率が高くなっているページを突き止めます。ランディングページからの導線がまずいと判断すれば、その部分を改善していくのです。
もしアクセス数が減っていた場合、リニューアルによってURLが変更されたので、検索エンジンや集客力の高い外部サイトからの流入が減っているか、titleタグなどを変更したために、検索エンジンから集客できていたキーワードで入ってこられなくなったユーザーが増えた等の原因が考えられます。流入元サイトや検索クエリを見て、その中で減っているものをチェックし改善していきましょう。