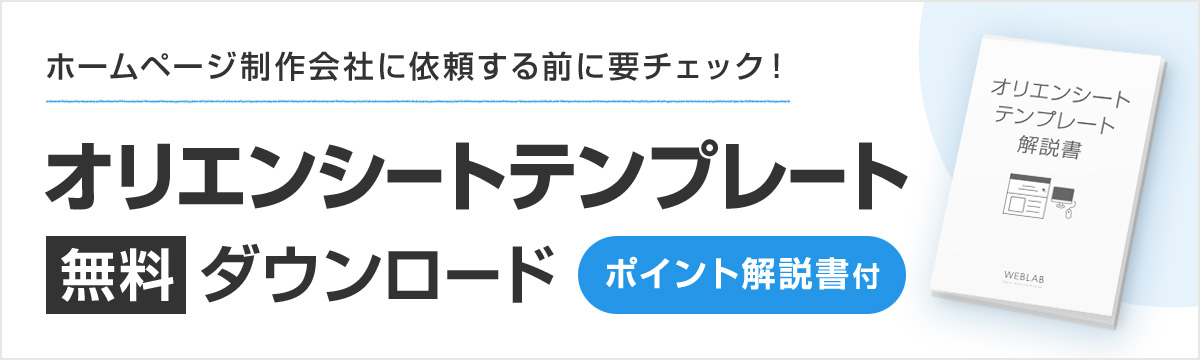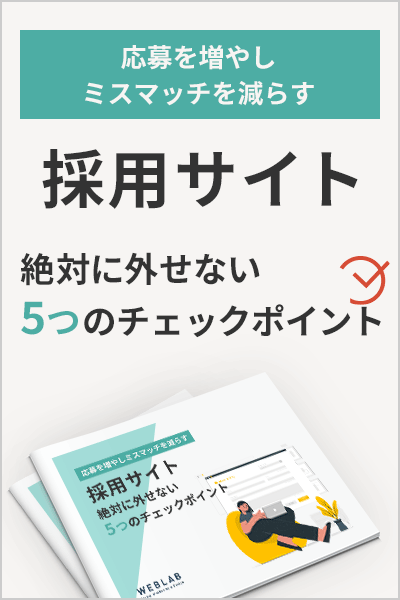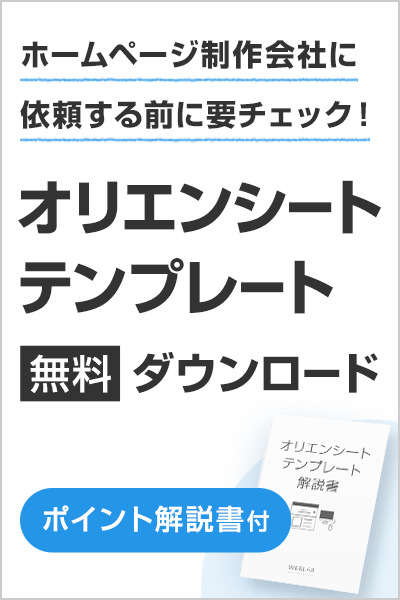ホームページ担当者なら気をつけたい!画像の著作権侵害とライセンス証明
 会社のホームページを更新する際、「素晴らしい写真があれば記事が映えるのに…」と思ったことはありませんか?そんなとき、インターネットで見つけた画像を使ってしまうと、思わぬトラブルに発展する可能性があります。
会社のホームページを更新する際、「素晴らしい写真があれば記事が映えるのに…」と思ったことはありませんか?そんなとき、インターネットで見つけた画像を使ってしまうと、思わぬトラブルに発展する可能性があります。
最近では、自治体や学校のホームページでさえ著作権侵害で問題になることがあり、「著作権侵害の通知が突然メールで届いた」という相談も珍しくありません。
しかし、正しい知識があれば、安心して画像を利用できます。今回は、ホームページ担当者が知っておくべき著作権の基礎知識やフリー素材の問題、トラブルへの対処法までわかりやすくご説明します。
そもそも著作権とは
まずは、著作権についてご説明します。
著作権とは
著作権とは、創作された文章、音楽、絵画、写真、映像などの「著作物」に対して、作者(著作権者)が有する権利のことです。著作権は、作品が創作された瞬間から自動的に発生し、特別な手続きをしなくても保護されます。
インターネットが普及した今では、誰でも簡単に情報を発信したり、画像や動画を共有したりできます。しかし、インターネット上にあるコンテンツもすべて誰かが作成した「著作物」です。無断で使用すると、著作権の侵害になる可能性があります。
著作物の例
 著作物には、以下のようなものが含まれます。
著作物には、以下のようなものが含まれます。
- 写真:プロが撮影したものだけでなく、スマホで撮った写真も対象です。
- 文章:ホームページ記事、新聞記事、商品説明文などが含まれます。
- イラスト、デザイン:ロゴやバナー、アイコンなども著作物です。
- 音楽、音声:効果音など、音に関するものは保護されます。
- 映像:YouTube動画は著作権の対象です。
- コード:HTMLやJavaScriptなども著作物です。
ホームページでは画像や文章などの著作物がたくさん利用されています。実は、完成したホームページ自体が著作物として保護されています。
著作物でないもの
すべてのものが著作権の対象になるわけではありません。たとえば、以下のようなものは著作物には該当しません。
- 事実やアイデア(例:「あの山は111mの高さがあることで知られている」)
- 法律や判例、行政文書
- 表やグラフ(データの羅列は著作物ではないが、独創的なデザインが施されている場合は保護されることがある)
著作物でないものであっても、これらを特徴的にまとめたり、独自の視点で表現したりすると、その「表現方法」に著作権が発生することもあります。たとえば、データを独自のグラフィックで表現した場合、そのデザインには著作権が発生します。
著作権侵害のリスク
著作権を侵害すると、著作権者から警告や損害賠償の請求を受ける可能性があります。特に、企業のホームページで無断使用した場合、社会的信用の低下や法的責任を問われることもあります。
たとえば、
- インターネットで見つけた画像を無断でホームページに掲載した
- 非常にデータが参考になったので、許可を得ることなく他社の掲載内容をコピーして自社サイトに掲載した
- 著作権フリー素材なのかを確認せずに、自社広告に利用した
これらの行為は、著作権侵害となる可能性が高いです。知らなかったでは済まされないケースもあるため、正しく著作権を理解し、対処しましょう。
無料・フリー素材の落とし穴
次に、無料・フリー素材の落とし穴についてご説明します。
インターネット上の画像の著作権
「インターネット上にある画像は自由に使えるんでしょ?」実はこれ、よくある誤解です。インターネット上で簡単に見つけられる画像やイラストも、誰かが作成した著作物です。Google画像検索で見つけた画像、SNSに投稿されている画像、他社のホームページにある写真など、これらはすべて原則として著作権者の許可なく使用することはできません。
画像を取得したり、保存したりする行為は簡単ですが、それが「許可なく使用してもいい」という意味ではないんです。特に、会社のホームページでの使用は「商用利用」となり、より厳しい目で見られることがほとんどです。
フリー素材は著作権フリーではない
「でもフリー素材って書いてあるから大丈夫ですよね?」これも要注意です。「フリー素材」と呼ばれるものでも、必ずしも「著作権フリー」という意味ではありません。多くの場合、「一定の条件のもとで無料で使える」というだけで、さまざまな利用制限が設けられていることがほとんどです。たとえば、よくある制限に次のようなものがあります。
- 商用利用の禁止:個人のホームページは問題なくても会社のホームページでは禁止
- クレジット表記の義務:「Photo by 名称」などの記載が必要
- 改変の禁止:画像の内容変更が禁止されている
- 用途の制限:ホームページでの利用は問題なくても、印刷物では別途許可が必要
- 再配布の禁止:他の人に渡すことができない
これらの条件を無視して使用すると「無料」のはずが、あとで高額な請求に繋がることもあります。
フリー素材をめぐる著作権トラブル
 テレビで放送されていますが、最近は公的機関でもフリー素材の利用で問題になるケースが増えています。仕事で必要だった画像を使った自治体に対し、運営会社が使用料の支払いを求める通知を送付しました。
テレビで放送されていますが、最近は公的機関でもフリー素材の利用で問題になるケースが増えています。仕事で必要だった画像を使った自治体に対し、運営会社が使用料の支払いを求める通知を送付しました。
問題の原因は「利用規約」を確認していないことです。ある小学校では、学校便りに使ったイラストが「商用利用禁止」だったことで問題になり10万円以上の請求を受けています。学校が「商用」に当たるかは議論の余地がありますが、結局は利用料を支払うことになったケースもあります。
町の広報誌として利用してしまった場合では、100万円を超える請求となっています。会社のホームページでは当然ながら非常に厳しくチェックされます。「ウチはまだ小さな会社だから…」と思っていても、ホームページが公開されていれば、誰でも見ることができます。権利者が見つけた場合、請求される可能性は十分にあるのです。
利用規約とルール
フリー素材を安全に利用するにはどうすればいいのでしょうか。最も重要なのは、必ず利用規約を読むことです。具体的には、以下の点に注意しましょう。
- 商用利用が可能か:会社のホームページで利用するなら、明確に「商用可能」と記載されているか確認
- クレジット表記の要否:必要な場合は、指定された方法で必ず表記する
- 利用可能な点数:ホームページによっては制限がある場合がある
- 利用目的の制限:ホームページに限定、印刷物は禁止、などの制限がないか
- 改変の可否:画像の内容変更などが許可されているか
そして大事なのが、「規約を画像として残しておく」ことです。後々のトラブル防止のため、素材を取得した日時と共に、当時の利用規約を保存しておくと安心です。というのも、フリー素材サイトが突然サービスを終了したり、規約が変更されたりすることもあるからです。
安全に使えるフリー素材は確かに便利ですが、「無料だから」と安易に利用するのではなく、ルールを理解したうえで利用することが大事です。結局のところ、数百円の有料素材を買った方が、後々のリスクを考えると安心でしょう。
著作権ラインセンス料の徴収代行とは
次に、著作権ラインセンス料の徴収代行についてご説明します。
ライセンス料の徴収代行
最近、インターネット上の著作権侵害を監視し、権利者に代わって使用料を請求する「ライセンス料の徴収代行サービス」があります。こうしたサービスは、AIやデジタル技術を利用して、インターネット上の膨大な画像から無断使用されている画像を検出し、使用者に連絡して使用料の支払いを求めるというものです。
特に、コピートラックという会社の名前を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。写真の権利者(主にフォトグラファーやストックフォト会社)と提携し、無断使用されている写真を見つけます。
コピートラックとは
「謎の会社から突然メールが!」そんな経験をした方もいるかもしれません。コピートラックは、著作権管理代行会社で特殊な画像認識技術を使って、インターネット上で無断使用されている写真を自動的に検出します。その仕組みは、次のとおりです。
- ステップ1:依頼者より権利保護の依頼を受ける
- ステップ2:独自の画像認識AIで、インターネット上から同一画像を検索
- ステップ3:無断使用が見つかると、使用者に連絡
- ステップ4:使用料の支払いを要求
- ステップ5:支払われたライセンス料の一部を権利者に還元
実際は、ある日突然メールが届くことから始まります。「あなたのホームページで使用されている写真は著作権侵害です。~日以内に使用料をお支払いください」といった内容で、支払わない場合は法的措置も辞さないことが記載されています。
金額は数万円から十数万円と、通常のストックフォトの使用料と比べてかなり高額なケースが多いのが特徴です。
ライセンス証明をするには
正規にライセンスを取得していた場合は、そのライセンス証明ができれば問題解決につながります。では、どうやって証明すればよいのでしょうか。主要なストックフォトサービスのライセンス確認方法は、次のとおりです。
Adobe Stock:名前を選び、ライセンス履歴でライセンス番号を取得できます。表示される番号は、ライセンス検証コードといいます。
PIXTA(ピクスタ):マイページの履歴で買った素材のライセンス情報を確認できます。
素材を取得する際には、以下のことを気をつけておくと安心です。
- ライセンス証明書や買った履歴について画像で残す
- 素材ファイルと一緒に保存しておく(フォルダ名に日付を入れるとよい)
- どのホームページで取得したかメモしておく
- 可能であれば、ファイル名も変更せずに保存する
これらの情報があれば、後で「この画像は買ったものです」と証明しやすくなります。
ライセンスが見つからない場合
本当に無断使用をしてしまっていたり、ライセンスの証明ができない場合は、どうすればよいのでしょうか。まずは、支払いを行う前に、会社の顧問弁護士に相談することをお勧めします。なぜなら、次のような理由があるためです。
- 請求額に問題がないか判断が必要
- 時効が成立している可能性もある
- 交渉により金額が減額できるケースがある
- 詐欺的な請求であることがありえる
弁護士に相談することで、対応策をたてられます。ただし、明らかに無断使用をしていた場合は、正しく対応することが会社としての信頼にもつながります。
こういった徴収代行会社の中には、弁護士法に抵触する「非弁行為」になる可能性がある行為を行っているケースもあります。そのため、法的な判断が必要な場面では、必ず専門家に相談することが大事です。
結局のところ、こうしたトラブルを防ぐには、最初から正規の方法で手に入れて、その証拠を残しておくことが最も確実な方法といえるでしょう。
素材選定時に気を付けたいポイント
次に、素材選定時に気を付けたいポイントについてご説明します。
安全に写真を使うには
ホームページ制作において、トラブルなく安心して素材を使うための基本的な考え方は「運営元がしっかりしている画像提供サービスを選ぶ」ということです。具体的には、次の3つの選択肢が安全です。
信頼できる大手ストックフォトサービスを利用する
Adobe Stockなどの大手ストックフォトサービスは、権利関係をしっかりと管理しているので比較的安心です。有料ではありますが、数百円〜数千円程度で利用できる素材も多く、後々のトラブルを考えれば、フリー素材よりは安心できる選択肢といえます。
自分(自社)で素材を用意する
最も確実なのは、自分や自社で写真を撮影したり、イラストを制作したりすることです。スマートフォンのカメラ性能も向上していますので、ちょっとした商品写真や社内の様子なら自前で撮影することも十分可能です。
最近は、AIによって自分で画像を作成することが可能になっています。「このような画像を作成してほしい」といった指示文を記載するだけで、著作権フリーの画像を作成できるため、自分で作成してみましょう。
ただし、AIで既存の著作物を模倣した場合や酷似している場合はトラブルになりかねませんので注意が必要です。また、他社の著作物を学習に使用している場合や、AIツールによっては商用利用禁止の場合もあります。AIツールを使う際も利用規約やポリシーはしっかりと確認しましょう。
フリー素材を慎重に選ぶ
フリー素材を利用する場合は、次の点に特に注意しましょう。
- 運営会社が明確なサービスを選ぶ:個人運営の小規模ホームページより、知られている会社が運営しているサービスの方が安心
- 利用規約を必ず確認:商用利用可能か、クレジット表記は必要か、使用点数制限はないか
- 特殊な用途には要注意:通常掲載は可能でも、印刷物、グッズ制作、アプリ内使用などは制限がある場合がある
- 規約の画像を保存:後々のトラブル防止のため、取得時の利用規約を証拠として残しておく
「何となくフリー素材のようなので大丈夫」と思って使うのが最も危険です。必ず画像の提供会社と利用条件を確認しましょう。
有料素材サイトの素材
有料のストックフォトサービスを利用すれば安心と思えますが、ここにも注意点があります。
運営元の信頼性
大手のストックフォトサービスは、素材の審査や権利関係の確認をしっかり行っているので比較的安心です。Adobe Stockなどは、何百万点もの素材を扱いながら、権利トラブルが少ないことで知られています。
著作権の保証範囲
どのような大手サービスでも「100%安全」という保証はありません。多くのサービスでは、利用規約に「著作権の保証」に関する記載がありますが、保証内容や補償範囲は会社によって次のように異なります。
- 画像の中心とする内容の著作権は保証しても、写り込んでいる商標や建築物については保証しない
- 補償額に上限がある
- 特定の使用方法は保証対象外
など、条件があるケースがほとんどです。利用前にサービスの保証範囲を確認しておくと安心です。
プロパティリリース・モデルリリース
人物が写っている写真には「モデルリリース」、特定の建物や私有地が写っている場合は「プロパティリリース」という許諾が必要になることがあります。多くのストックフォトサービスでは、素材の詳細ページにこれらの有無が記載されています。
モデルリリースあり:広告など商用利用が可能
モデルリリースなし:報道や編集目的で使用可能
特に広告や商品販売に関わる用途では、必ずこれらについての承諾がある画像を選びましょう。
透かし入り素材の差し替え忘れ
ストックフォトサービスでは、購入前に「透かし」入りの画像を確認できます。この透かし入り画像をそのまま使ってしまい、後で「無断使用」と指摘されるケースが意外と多いんです。
素材購入後は必ず、透かしのない正規の画像に差し替えたことを確認しましょう。特にウェブサイトのリニューアル時など、複数の担当者が関わる場合は要注意です。
自分(自社)で撮影した写真素材
「自分で撮ったから大丈夫」と思いがちですが、自前の画像にも注意点があります。
社内の人物写真と肖像権
自社の従業員であっても、その写真を公開するには本人の同意が必要です。特に採用ページや社内の様子を紹介するコンテンツでは、写っている社員に「肖像権使用同意書」を取得しておくのが良いでしょう。退職後のトラブルを防ぐためにも、書面での同意を得ておくと安心です。
写り込みに注意
自社オフィスや商品の写真を撮影する際、背景に写り込むものに注意が必要です。
- 他社の商標やロゴ:オフィスに置いてあるパソコンのメーカーロゴなど
- 有名建築物:背景にある特徴的な建物
- アート作品:オフィスに飾っている絵画やポスター
- 書籍や雑誌:デスクに置いてある本の表紙
これらが写り込んでいると、別の権利処理が必要になることがあります。撮影前に背景をチェックし、必要に応じてぼかし処理を施すなどの対応が安全です。
商品写真の場合
自社商品の写真でも、そのデザインに他社キャラクターなどが使われている場合は、そのライセンス条件を確認する必要があります。たとえば、ディズニーキャラクターの商品を販売している場合、その商品写真の使用にも制限がある場合があります。
結局のところ、どのような画像を利用するにしても「権利関係をしっかりと確認する」「証拠を残しておく」という基本姿勢が大事です。ちょっとした手間と意識が、後々の大きなトラブルを防いでくれるのです。
まとめ
ホームページに利用する画像の著作権問題は、会社の信頼性に繋がる重要な問題です。「インターネットで見つけた写真だから」「フリー素材だから大丈夫」という安易な判断が、後々のトラブルに繋がることも少なくありません。
特に注意したいのは、ある日突然、権利者やその代行会社から連絡が来る可能性があるということです。数年前に使用した画像でも、著作権侵害として高額な請求を受けるケースが増えています。
このようなトラブルがSNSなどで拡散されれば、企業イメージやブランド価値に大きなダメージとなります。安全にホームページを運営するためには、信頼できるストックフォトサービスの利用や、利用条件の確認、ライセンス証明の保存などが大切です。少しの手間と意識が将来の大きなリスクから会社を守ります。著作権の知識をつけ、正しい方法でホームページを運営していきましょう。
関連記事こちらの記事も合わせてどうぞ。